おはようございます。shionです。
今回は、私が一級建築士学科試験に合格した勉強スケジュールについてご紹介させていただきます。
私は大手の資格学校に通わないで学科試験に合格したため、今回の内容は独学者や学生にとって参考になる部分が多いのかなと思います。
ぜひ参考にしてみてください。
勉強スケジュール
早速ですが、月別の勉強内容についてまとめています。私は勉強を始めたのが、試験の前年11月中旬からでしたので、下記のようになっています。
勉強スケジュール
11月 計画、環境・設備
12月 施工と構造をメインに+α法規、計画等の復習もしながら
1月 法規メイン、その他復習
2月 過去問メイン、その他復習
3-6月 模試を受けつつ復習
7月 復習 → 学科試験
勉強期間としては、約8か月(勉強時間は約680時間)でした。
最初の目標は、とりあえず1つの科目の勉強を1周することにして、次の科目に移っても復習をしつつ全体を1周しましょう。
私が計画、環境・設備から勉強を始めた理由はとりあえず1周できそうと思ったからです。。
✅ 私が使用した教材について
教科ごとの勉強時間
細かく勉強時間を測ったわけではありませんが、勉強に掛かった時間順に科目を並べると、
法規 > 構造 > 施工 > 計画 ≧ 環境・設備
の順に勉強時間がかかりました。
まず、法規ですが法令集への線引きという作業に時間がかかる事と問題慣れにも時間がかかるため、一番時間を要しました。ちなみにおすすめの法規科目の参考書は、法規のウラ指導とTACの法令集です。9割取れました。とってもよかったので、今度記事にします。
線引き作業を年末年始で行い、1月は法規の問題慣れに時間を多く充てました。
構造、施工は単純に量が多くて、1周するのに時間がかかります。そして、馴染みのない用語が多数でてくるため、その用語の意味を調べるためにも時間がかかってしまいます。
計画、環境・設備は、法規や構造、施工と比べると範囲は狭く1周するのに時間がかかりません。ただし、計画科目の建築事例問題に関しては一気に覚えるのはかなり難しいですので、スキマ時間などにじっくり勉強しましょう。私自身もかなり苦労しましたので、その経験からnoteに事例をまとめたものを作成しましたのでぜひ参考になればと思います。
過去問と模試について
ある程度学習が進んだら過去問を1年分解いてみます。
その時点で、どの分野が苦手なのか・どれだけ時間がかかるのかを把握します。
そうしたら、その分野の復習をしてまた1年分過去問を解きます。これを繰り返していくと、分からない分野を潰してかつ試験時間にも慣れることができます。
大手の資格学校による模試もあり、その資格学校に通っていなくても受けることができますので、場慣れのために1回は受けるようにしましょう。
一番大事なのは復習
私が学科試験を受けるにあたって、一番大事だなと思ったのが「復習」です。
一問一答でも過去問を解くでも、自分が分からなかった問題に必ずチェックを入れるようにしていました。
そして復習の時間を設けて、チェックした問題を解説無しでも解けるようにします。
不安がなくなれば、チェックを外します。そしてまた、分からなかった問題が出たらチェックをして、不安がなくなるまで復習します。
ちなみに私がメインで使っていた教材はスタディングというオンライン型講座で、メモ機能やノート機能があったため重宝していました。
まとめ
今回は、一級建築士学科試験に独学で合格したスケジュールを紹介しました。
勉強期間としては、約8か月(勉強時間は約680時間)かかり、法規 > 構造 > 施工 > 計画 ≧ 環境・設備の順に時間を要しました。
そして、最も時間がかかるのが復習です!必ず分からない問題にはチェックを入れて復習しましょう。
おすすめのメイン教材はスタディングです。下記も併せてぜひ参考にしてみて下さい!
✅ 私が使用した教材について
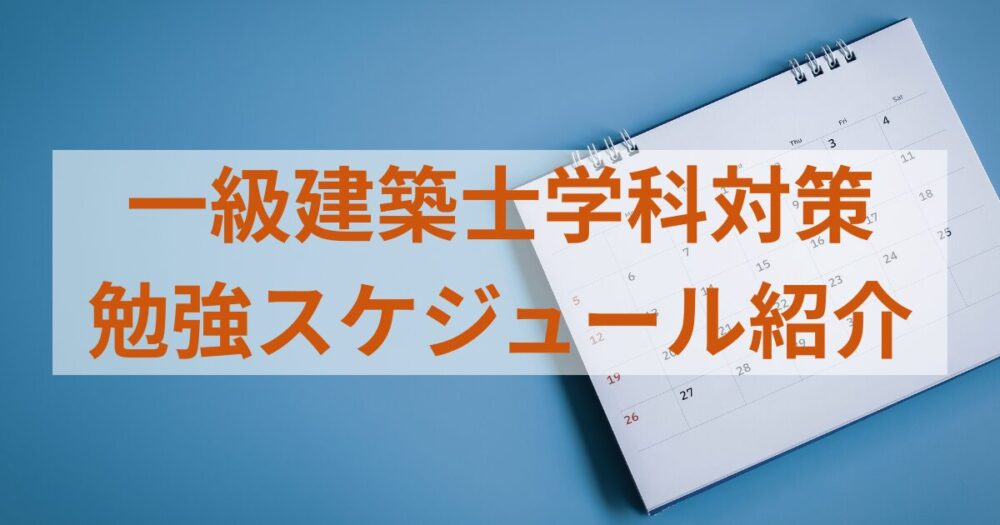

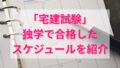
コメント