一級建築士「計画」科目に出題される建築事例について過去10年以上(2025年分除く)の事例をまとめております。
一級建築士を目指す方は参考としてぜひご活用いただけたらと思います。また、建築が好きな方にも新たな出会いがあればと思います。
建築事例をマッピングしておりますので、参考になれば幸いです。※解体や個人宅等の理由でマッピングされていない事例もございます。
下記画像のようにコメントを入れてマッピングしています!

事例は、pdfデータとしてもダウンロードできるようにしております↓↓↓
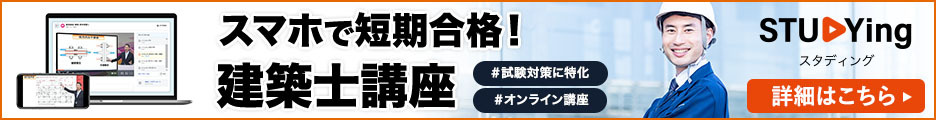
図書館
日本の図書館建築
日野市立中央図書館(東京都、1973年)は、成人開架と児童開架をL字型平面に振り分け、自習室を設けず、閲覧席を少数にするなど、貸出を重視した図書館である。
国際子ども図書館(東京都、2002 年)は、日本で唯一の国立の児童書専門図書館であり、明治39年(1906年)に建設された鉄骨レンガ造の帝国図書館を再生・利活用している。免震工事が行われ、改修されたエントランス部分は、ガラスのボックスを旧建築に挿入したような構成になっている。
朝霞市立図書館本館(埼玉県、1987 年)は、床面積と開架冊数の量的拡大、館内読書や調べ物への対応という質的変化、住民の交流拠点等に応える様々なコーナーを設けた図書館である。中央部のトップライトのある八角形の吹き抜け空間も特徴である。
まちとしょテラソ[小布施町立図書館](長野県、2009 年)は、間仕切りを必要最小限に抑えることで大空間を実現させ、三角形平面プランの中央に開架書庫を配置し、3 つの辺に沿って緩やかに分けられたスペースがつくられている。
金沢市立玉川図書館(石川県、1979 年)は、東側の開架部門と、中庭を挟んで西側にある学習・管理部門を分けることによって、開架部門を気軽に立ち寄り利用できる空間とした図書館 である。
国立国会図書館関西館(京都、2002年)は、書庫を地下に、中庭に面した閲覧室を半地下に配置することで建築物の地上部分のボリュームを抑え、景観上の調和に配慮した図書館である。 また、書庫及び閲覧室を地階に設けることで、管理上、職員と利用者との動線を明確に分離している。
苅田町立図書館本館(福岡県、1990 年)は、多様な閲覧席と豊富な資料を備え、開架書架群に沿ってベンチ、和室、屋外読書スペースなどを設けることで、来館者が長い時間を過ごせるように計画した図書館である。
海外の図書館建築
フランス国立図書館(フランス、1995 年)は、敷地中央部に緑豊かな中庭をもつロの字型の基壇部と、その四隅に配置されたL宇型の高層タワーから構成されている。
デンマーク王立図書館(デンマーク、1999 年)は、既存の王立図書館(旧館)に対し、道路を挟んだ運河側に黒色のガラス張りの新館(通称:ブラック・ダイアモンド)が増築され、メインエントランスは新館に設けられている。
ベルリン自由大学図書館(ドイツ、2005年)は、外壁が二重構成のドームで覆われ、内部は白色で統一され、特徴的な形状と省エネルギーを重視した画期的な機能から「ベルリンの脳」とも呼ばれている。
ストックホルム市立図書館(スウェーデン、1928年)は、円筒と直方体が組み合わされた外観をもち、巨大な円筒の内部には、壁に沿って書架があり、中央にサービスデスクが設けられている。
英国図書館セントパンクラス館(イギリス、1997年)は、大きな三つのゾーンからなり、前庭から入る中央ゾーンは、傾斜屋根により高い天井高を有し、中央にガラス張りの積層式書架形式のライブラリーがある。
シアトル中央図書館(アメリカ、2004年)は、外観全体が格子状の鉄骨とガラスで構成され、室内空間に外光を導いている。
新アレクサンドリア図書館(エジプト、2002年)は、傾斜した巨大な円盤状の屋根構造をもち、外壁には世界各地・各時代の文字が彫り込まれている。
美術館
日本の美術館建築
金沢21世紀美術館(石川県)は、誰でも気軽に様々な方向から立ち寄れるように、複数のエントランスのある円形の平面とし、内部には建築物の端から端まで見通すことができるいくつかの廊下がある。
富弘美術館(群馬県)は、シャボン玉をイメージした正方形の建物で、円筒状の大小33の部屋があつまった廊下も柱もない造りとなっている。
石の美術館(栃木県、設計:隈研吾)は、米を貯蔵していた石蔵を美術館として再生しており、地場産の石材を用いた試みが特徴の建築物である。
那珂川町馬頭広重美術館(栃木県、設計:隈研吾)は、美術館全体は、地元産の杉材によるルーバーに包まれ、自然豊かな景観に溶け込むよう、平屋建てに切妻の大屋根を採用している。
世田谷美術館(東京都)は、公園内に立地するため、周辺環境との調和を重視し、高さは2階と低く抑え、建築群を回廊でつないだ施設である。
国立西洋美術館(東京都、ル・コルビュジエ)の改修においては、免震レトロフィット工法を採用し、竣工時の形を損なうことなく地震に対する安全性を高めている。
東京国立近代美術館工芸館(東京都)は、明治時代に旧近衛師団司令部庁舎として建設された赤レンガ造の洋風建築を活用した美術館である。(2020年10月に石川県金沢市に移転)
3331 Arts Chiyoda(東京都)は、廃校になった中学校を、アートギャラリーを含む文化施設として保存・再生させたものである。(2023年に閉館)
千葉市美術館(千葉県)は、昭和初期に銀行として建設された既存建築物全体を新築の建築物で覆う「鞘堂(さやどう) 」という日本古来の方式により整備したものである。
ポーラ美術館(神奈川県)は、周囲の景観を極力損なわないよう、すり鉢状の構造体を地下に埋め込んで建築物の高さを抑え、美術館の中心を貫くアトリウムにより自然光を取り入れることで、自然と美術との共生を目指した空間が計画されている。
京都市京セラ美術館[京都市美術館](京都府)は、昭和初期に開館した美術館の既存のメインエントランスを残し、スロープからつながる地下広場に面した新たなエントランスを設けるなどの改修がされている。現存する日本の公立美術館の中でもっとも古い建築であり、帝冠様式を代表する建築である。
犬島精錬所美術館(岡山県)は、20世紀初頭に閉鎖された精錬所の遺構を活用し、 自然エネルギーを積極的に利用した美術館として保存・再生させたものである。
豊島美術館(香川県)は、鉄筋コンクリートのシェル構造による屋根の大きな開口部から、周囲の風・音・光を内部に直接取り込むことで、周辺環境と建築物、展示作品とを一体で感じられるように計画されている。
丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(香川県)は、建築と美術と都市空間が一体となった景観に寄与しており、駅前の広場に面した壁画部分に入口をもつ施設である。
海外の美術館建築
ニューヨーク近代美術館(アメリカ、設計:谷口吉生)は、敷地の北側と南側に通抜けが可能なエントランスホールがあり、中庭と連続する空間となっている。
ロサンゼルス現代美術館(アメリカ、設計:磯崎新)は、赤砂岩の外壁をもつ基壇部があり、その基壇部の上にピラミッド型のトップライト等が配置されている低層の建築物である。
フォートワース現代美術館(アメリカ、設計:安藤忠雄)は、平行に並べられた長方形の室によって展示室が構成され、その展示室には日差しへの配慮から深い庇が掛けられている。ガラスカーテンウォールとY字型の柱、周りを囲む池に映る姿が特徴的である。
キンベル美術館(アメリカ、設計:ルイス・カーン)は、ヴォールト屋根と頂部に設けられたトップライトの構成を特徴とする建築物である。
アスペン美術館(アメリカ、設計:坂茂)は、格子状に編んだ木製のスクリーンとガラスカーテンウォールに囲まれた大階段、木製の屋根架構をもつ建築物である。
ソロモン・グッゲンハイム美術館(アメリカ、設計:フランク・ロイド・ライト)は、建築物の中央部にアトリウムがあり、アトリウムに面した螺旋状のスロープによって、最上階から地上階まで連続した空間となるように計画されている。
カステルヴェッキオ美術館(イタリア)は、14世紀に建設された歴史的建造物である城を、美術館等として保存・再生させたものである。
ビルバオ・グッゲンハイム美術館(スペイン、設計:フランク・ゲーリー)は、彫塑的な形態であり、三層にわたる展示空間が中央アトリウムを囲うように配置されている。
オルセー美術館(フランス パリ)は、鉄道の駅舎を印象派の作品を中心とする美術館へ再生させたものである。
テイト・モダン(イギリス ロンドン)は、第二次世界大戦後の復興時に建設された火力発電所をモダンアートの美術館へ再生させたものである。
博物館
東京国立博物館本館(東京都)は、二つの中庭をもつ「日の字型」の平面で、中庭の周囲に展示室を配置している。帝冠様式の代表例である。
鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム(旧神奈川県立近代美術館鎌倉館)(神奈川県)は、坂倉準三が設計した神奈川県立近代美術館鎌倉館を耐震補強等を行ったうえで、博物館として整備したものである。
潟博物館(新潟県、設計:青木淳)は、螺旋(らせん)状の動線空間で構成された博物館であり、周囲の自然観察と展望が可能な施設である。
海の博物館展示棟(三重県)は、漁船や漁具を保存・展示する博物館である。展示棟は、木造の大架構による開放的な展示空間となっており、瓦屋根に外壁は杉板が使用されている。
京都文化博物館の別館(京都府、設計:辰野金吾)は、平安博物館として使用されていた旧日本銀行京都支店を、竣工時の姿に復元し、整備したものである。
近つ飛鳥博物館(大阪府)は、屋根全体を大階段の展望広場とし、その大階段を二分するスリット状のアプローチが人々をエントランスに導くように計画された。
八代市立博物館(未来の森ミュージアム)(熊本県)は、公園の一角に築かれた丘に埋まるように1階の展示室があり、2階にエントランス、最上階に収蔵庫が設置されている。
大英博物館 (イギリス)は、考古学の成果に基づく古代ギリシアや古代ローマ建築の研究及び正確な理解を通じ、その造形原理の復興を試みた新古典主義を背景としている。
アイアンブリッジ峡谷博物館(イギリス)は、複数の産業・土木遺構を現地で再生して展示し、環境教育の場としている。
文化・複合施設等
サッポロファクトリー(北海道)は、明治初期に建設された工場を商業施設に改修し、中央に設けたガラス屋根のアトリウムを市民に開放することで、公共性の高い空間を実現した。
豊平館(北海道)は、木造総2階建てで、中央入口の上部に架かる半円形に張り出したバルコニーをコリント式の柱で支える、明治時代に建てられた洋風の建築物である。
せんだいメディアテーク(宮城県)は、各階の大空間を構成するプレートを13本のチューブが貫き、市民ギャラリー、図書館、映像センター等が複合した施設である。
福島県産業交流館(通称:ビッグパレットふくしま)は、楕円に近い形状をもつ「マザールーフ」と呼ばれる大屋根に特徴があり、「ビッグパレット」の由来となっている。
太田市美術館・図書館(群馬県)は、建築物の屋内外を巡るスロープや階段、テラス、緑化された屋上を備え、駅前からは施設の賑わいが見え、また、施設からは街が眺められるように計画された。
群馬県農業技術センター(群馬県)は、小断面の製材を格子状に組み合わせた屋根架構をもつ建築物である。
水戸芸術館(茨城県)は、音楽、演劇、美術のそれぞれに対応した文化施設を、個々の空間の独立性を保ちながら、一体化させている。
代官山ヒルサイドテラス(東京都)は、住宅、商業施設、オフィス、レストラン等の機能が複合し、建築群が内包する広場や路地等を主要素として外部空間を形成し、周囲の純和式建築物や庭園とゲートによってつながるように計画された。
自由学園明日館(東京都)は、F.L.ライトと遠藤新とが設計した木造校舎であり、国の重要文化財の指定を受けて、使い勝手を向上させながら耐震補強等の改修がなされ、現在では結婚式やパーティーにも利用されている。
東京国際展示場(通称:東京ビッグサイト)は、4本の巨大な柱によるスーパーストラクチャーによって支えられた「コングレスタワー」と呼ばれる会議棟が施設のシンボルとなっている。
千葉県日本コンベンションセンター国際展示場(通称:幕張メッセ)は、シルエットが山並みをイメージさせる第1期計画の建築物と、屋根形状が凹面から凸面に波のように変化する第2期計画の建築物があり、これらがつくりだすスカイラインに特徴がある。
横浜赤レンガ倉庫(神奈川県)は、明治時代末期から大正時代初期に建築された煉瓦造の倉庫を改修し、文化施設、商業施設として整備した建築物である。
横浜国際平和会議場(通称:パシフィコ横浜)は、国際会議場、展示ホール、ホテル等からなる複合施設で、押し寄せる波、水面から屹立(きつりつ)する大きな帆、ヨットのキールの形態など、海にちなむモチーフで計画されている。
アオーレ長岡(新潟県)は、駅前に建てられた市民協働・市民交流の拠点であり、大通りに開かれた屋根付き広場を中心に、アリーナ、市民交流スペース、市役所、議会等を配置した複合施設として計画された。
新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ)(新潟県)は、本体施設の屋上庭園と複数の浮島状の空中庭園が回遊性をもつペデストリアンデッキで結ばれ、公園と一体化したパブリックスペースを形成している。
金沢市民芸術村(石川県)は、大正から昭和初期に建設された紡績工場の倉庫を改修し、工房、 レストラン、オープンスペース等から構成される芸術文化施設へ再生させたものである。
ぎふメディアコスモス(岐阜県)は、木造格子屋根をもつ市立中央図書館や、市民活動交流センター、多文化交流プラザ及び展示ギャラリー等からなる複合施設である。
愛知県児童総合センター(愛知県)は、チャレンジタワーと呼ぶ吹抜け空間を中心としたアトリウムを取り囲むように創作活動諸室、体験諸室、幼児コーナー等が配置された児童施設である。
ロームシアター京都(旧京都会館)(京都府)は、昭和30年代に建設された既存建築物を保存し、 意匠的な要素を再現しながら、増築と一部建て替えを行うことで、機能拡充が図られたものである。
TIMEʼS Ⅰ,Ⅱ(京都府)は、ヴォールト屋根で水平性の軸性を持ったⅠ期部分に、ドームの屋根を持ったⅡ期が増築されている商業施設である。1階のテラスはほとんど川の水面レベルにあり、人と水とのふれあいの場となっている。
倉敷アイビースクエア(岡山県)は、連続するのこぎり屋根をもつ平家建ての紡績工場の棟の一部を撤去してできたオープンスペースを中心として、展示施設、ホテル等からなる複合施設にしたものである。
出雲ドーム(島根県)は、集成材とケーブル等で構成された立体張弦アーチと、膜屋根を組み合わせた架構をもつ建築物である。
アートプラザ(大分県)は、磯崎新が設計した大分県立図書館を、ギャラリー等からなる芸術文化の複合施設にしたものである。
熊本県立劇場(熊本県)は、来館者の動線を円滑にエントランス空間に導くために、演劇ホールとコンサートホールの間に光庭や吹抜けをもつモール状の空間を設けている。
沖縄コンベンションセンター(沖縄県)パーゴラのある中央広場を囲むように、劇場棟、展示棟及び会議棟が配置されており、屋根の形状については大空に羽ばたく鳳がイメージされている。
ミレニアムドーム 2000 (イギリス):直径約365 m・最高高さ約 50 mの膜構造ドームは、 12 本のマストの頂部からケーブルで吊られている。
リンゴット工場再開発計画(イタリア)は、巨大な自動車工場を、音楽ホール、見本市会場、ホテル、事務所、店舗等からなる複合施設へ転換させたプロジェクトである。
デッサウのバウハウス校舎(ドイツ)は、宿舎兼アトリエ、工房、付属工業学校という三つの機能をそれぞれ独立したブロックにしたことが特徴である。
ベルリン・フィルハーモニーホール(ドイツ)は、ハンス・シャロウンにより設計された音楽ホールで、舞台を中央に配置し、客席がそれを囲むように傾斜配置されたヴィンヤード型(ぶどう畑型)の空間構成を特徴とする。
アラブ世界研究所(フランス)は、図書館、博物館、展示室等からなる複合施設であり、南北二つの棟がスリット状の通路及び正方形の中庭を挟んで対峙する構成となっている。
シドニー・オペラハウス(オーストラリア)は、国際コンペによって選ばれたヨーン・ウツソンが設計したオペラハウスで、円弧のシェル群によるシンボリックな造形が特徴である。
学校等
公立はこだて未来大学(北海道)は、吹抜けの大空間に面して、機能を特定しないスタジオを雛壇状に設けている。
棚倉町立社川小学校(福島県)は、クラスルーム、オープンスペース及びテラス等を、低、中、高学年ごとにまとめたユニットとし、各ユニット、多目的ホール及び屋外劇場を、中庭を巡るスロープで結んでいる。
宮代町立笠原小学校(埼玉県)は、クラスルームの床面積を通常の約1.5倍とし、クラスルーム内に畳コーナー、ベンチ等のあるアルコーブ(壁の一部を後退させてつくったくぼみのようなスペース)を設けている。
目黒区立宮前小学校(東京都)は、オープンスクール形式を採用しており、オープンスペースをメディアスペース(VTR・スライド・OHP学習コーナー等)と組み合わせた計画が特徴である。
ふじようちえん(東京都)は、屋内の間仕切壁が少なく、引戸の多用により屋外ともつながる広々とした空間の上に、自由に走り回れる円環状のウッドデッキを設けた屋根がある幼稚園である。
千葉市立打瀬小学校(千葉県)は、オープンスクール形式が採用され、クラスルーム、ワークスペース(オープンスペース)、アルコーブ、中庭等をひとまとまりにした空間を、低、中、高学年ごとに配置し、多様な学習展開への対応を図っている。
加藤学園暁秀初等学校(静岡県)は、学習センターを中心として、オープンクラスルーム(16m×16m)と特別教室を中庭を介して配置している。日本で初めてオープンスクール方式が採用された実例である。
東浦町立緒川小学校(愛知県)は、教室間の壁を可動式としたオープンスペースによる施設計画が特徴です。
旧開智学校校舎(長野県)は、アーチや隅石等の洋風の意匠と唐破風等の和風の意匠が混在した擬洋風の建築物である。
阿智村立浪合学校(長野県)は、ランチルームに音楽室を隣接させてオーディトリウムの機能をもたせて地域の利用も可能とし、また、村の教育・文化施設の中心として、保育園、小・中学校、公民館を併設した。
立命館大学大阪いばらきキャンパス(大阪府)は、工場跡地において、官民が連携し、防災公園と一体化して計画された。
福岡市立博多小学校(福岡県)は、オープンプラン型を採用し、旧来型の職員室の代わりに壁のない教員コーナーやワーキングスペースを設けることで、複数の教員で児童を見守ることのできる空間整備が行われた。
独立住宅
日本の独立住宅
まつかわぼっくす(東京都、設計:宮脇檀)は、三方を建物、一方を壁によって中庭を囲まれたコートハウスで、RC造と木造による混構造の住宅である。
ヴィッラ・クゥクゥ(東京都、設計:吉阪隆正)は、コンクリートの特性を生かした形態と彫りの深い開口をもち、外部に対して閉じることにより「閉鎖性」をつくり出したワンルーム形式の住宅である。
土浦亀城邸(東京都)は、「白い箱」型の外観をもち、内部は居間の吹抜けを中心とし複数の床レベルによって構成されたモダニズムの木造住宅である。(2024年に港区に移転し復元されました)
スカイハウス(東京都、菊竹清訓)は、住宅生産の工業化の利点を生かし、設備等の更新を可能とする「ムーブネット」を取り付けた住宅である。また、メタボリズムの考え方に基づき、一辺約10mの正方形平面の生活空間とHPシェルの屋根が、4枚の壁柱で空中に支えられた住宅である。
前川自邸(東京都、前川 國男)は、外観は切麦屋根の和風、内部は吹抜けの居間を中心に書斎・寝室等を配した木造モダニズム建築である。(当時は品川区に建てられていた自邸ですが、現在は江戸・東京たてもの園に保存・展示されています)
シルバーハット(東京都、伊東豊雄)は、鉄筋コンクリートの柱の上に鉄骨フレームの屋根を架け、コートの上部に吊られた開閉可能なテントにより通風や日照を調節することで、コートを半屋外空間として利用することができる。(伊東自邸、現在は愛媛県の伊東豊雄建築ミュージアムに移築されています)
中野本町の家(東京都、設計:伊東豊雄)は、U字型の外部から閉ざされた空間構成のRC造の住宅である。(解体されています)
から傘の家(東京都、篠原一男)は、方形屋根で覆った正方形の単一空間を用途によって分割した、造形性の高い全体構成をもつ。(解体されています)
私たちの家(東京都、林昌二・林雅子)は、庭と居間とが面する関係を保ちつつ、コンクリートブロック造の住宅を増改築することで、夫婦2人の住まいとした住宅である。
増沢邸[自邸](東京都、増沢洵)は、戦後の極限的小住宅の先駆けとなった事例であり、3間×3間の9坪の平面プランをもつ2階建ての計画であり、3坪の吹抜けに面して設けた南面大開口部の障子を通して、柔らかな光を室内に取り込んだ住宅である。
斎藤助教授の家(東京都、清家清)は、テラス、廊下、居間が連続する開放的な平面に、移動畳等を配置し、場面に応じて空間を設える「舗設(ほせつ)」の概念を具現化した住宅である。
正面のない家-H(兵庫県、坂倉準三建築研究所)は、敷地全体を壁によって囲い込み、四つに分かれた庭が各室に採光と広がりを与えているコートハウスである。
原自邸(東京都、原 広司)は、玄関からバルコニーまで降りてゆく中央の吹抜けの両側に居室を配置し、トップライトから自然光を取り入れ、住居の中に「都市を埋蔵する」構成を意図した住宅といわれている。
塔の家(東京都、設計:東孝光)は、小面積で不整形な敷地条件に対し、住空間を機能別に積層して構成した都市住宅である。
立体最小限住居(東京都、池辺陽)は、工業化住宅の試みとして発表された「15坪住宅」であり、吹抜け空間を設けることで、狭小性の克服を目指した住宅である。
夫婦屋根の家(神奈川県、山下和正)は、1階を生活部分、2階を仕事場に分けた明快な平面構成が特徴である。2階のアトリエとピアノ室は、それぞれトップライトのある寄棟屋根としている。
軽井沢の山荘(長野県、吉村順三)は、片流れの屋根と2階の居間を中心とした平面計画が特徴である。1階の鉄筋コンクリート造のコアの上の木造部分に、最小限必要な要素を収めた住宅である。
聴竹居(京都)は、「日本の住宅」の著者である藤井厚二により設計された自邸で、通風・採光・断熱などの環境要素を建築計画に取り入れた設計がなされ、日本におけるパッシブデザインの先駆例とされる。
住吉の長屋(大阪府、設計:安藤忠雄)は、ファサード玄関以外の開口部がなく、住宅の中央部に光庭を設けた住宅である。
グラバー邸(長崎県)は、日本に現存する最古の木造西洋風建築である。
海外の独立住宅
ガラスの家(アメリカ、フィリップ・ジョンソン)は、林の中にある広大な敷地に建つ週末住宅であり、暖炉とコアによる明快な平面構成を持つワンルーム空間の住宅である。
ファンズワース邸(アメリカ、ミース・ファン・デル・ローエ)は、広大な敷地に建つ週末住宅であり、H型鋼の柱に溶接された梁を介して屋根スラブ及び床スラブを取り付けた構造(鉄骨造)とユニバーサル空間が特徴である。ユニバーサル空間とは:必要に応じて、間仕切りや家具を配置することで、いかなる用途にも対応できるようにつくられた空間のこと。
ロビー邸(アメリカ、設計:フランク・ロイド・ライト)は、プレーリーハウスの典型例とされ、軒を深く出して水平線を強調し、煙突の垂直線と対比させた住宅である。
落水荘(アメリカ、フランク・ロイド・ライト)は、2層の床スラブが滝のある渓流の上に張り出し、周囲の自然の眺めを味わえるように意図された住宅である。
イームズ自邸(アメリカ、チャールズ&レイ・イームズ)は、再組立が可能という理念のもと、形鋼やスチールサッシ等工業製品を用いて建築された住宅である。
ゲーリー自邸(アメリカ、フランク・O・ゲーリー)は、既存の木造住宅に、安価な材料である金網やトタン板、ベニヤ板の断片等を組み合わせて増改築を行った、ポストモダンを代表する住宅の一つである。
フィッシャー邸(アメリカ、ルイス・カーン)は、二つの矩形のボリュームが45度の角度をもって接合され、一方には2層の個室群が配置され、もう一方には2層分の高さの居間をもつ、幾何学的な構成の住宅である。
バラガン自邸(メキシコ、ルイス・バラガン)は、庭と分かち難く結びついた内部空間をもち、 居間の奥には庭に面して大きな窓を設け、積極的に外部を内部に取り込んだ住宅である。
ヒラルディ邸(メキシコ、ルイス・バラガン)は、ショッキングピンクの外観で、壁のスリット、室内のプール、中庭などが設けられ、光が室内の様々な色の壁や水面に降り注ぎ、光と色が競演する空間となっている。
クルチェット邸(アルゼンチン、ル・コルビュジェ)は、不整形敷地に建つ地上4階建ての医院併用住宅であり、台形の平面をもつ医院と矩形の平面をもつ住居は、中庭のスロープで繋がれている。
夏の家(スウェーデン、E. G. アスプルンド)は、切妻屋根の2棟が組み合わさった形状であり、主棟に対し、居間棟をずらして配置することで、主棟にあるホール(食堂)からも海を見渡せるようにした住宅である。
シュレーダー邸 (オランダ、ヘリット・リートフェルト)は、建具や家具による住空間づくりに特徴があり、無彩色と青・赤・黄の三原色が組み合わされたデ・スタイルの構成原理を具現した住宅である。
タッセル邸 (ベルギー、ヴィクトール・オルタ)は、植物の茎や葉、長い髪などの自然物をモチーフとした非対称な曲線や曲面を造形に用いたアール・ヌーヴォーを背景としている。
レッド・ハウス(赤い家)(イギリス)は、アーツ・アンド・クラフツ運動(機械生産を否定し、手仕事を尊重した工芸革新運動)を主導したウィリアム・モリスの自宅兼工房である。
ダルザス邸(ガラスの家)(フランス、ピエール・シャロー)は、南北全面を半透明のガラスブロック壁とし、間仕切り壁にガラスやパンチングメタルを使うことで、内部まで明るい一塊の空間とした住宅である。
サヴォア邸(フランス):ル・コルビュジェは、近代建築の5原則として、「ピロティ、屋上庭園、自由な平面、水平連続窓、自由なファサード」を提示し、この原則を具現させた作品である。
バワ自邸(スリランカ、Number 11)は、4 軒長屋を改造・改築することにより、路地を長い回廊に置き換え、アプローチから建築物の深部に至るまでに坪庭が随所に設けられた住宅である。
集合住宅
日本の集合住宅
釜石・平田地区仮設住宅団地(岩手県、2011 年)は、東日本大震災の復興支援の一環として建設されたコミュニティケア型仮設住宅団地であり、高齢者向け住戸と一般向け住戸で構成され、診療所付きのサポートセンターや仮設店舗が計画された。
並柳HOPE住宅(宮城県)は、北からの強風と地吹雪を防ぐ屋敷林や瓦屋根と漆喰壁による景観によって周辺の風景との調和を図り、地場産材の活用等による地域の活性化を意図した戸建て住宅団地である。
茨城県営六番池アパート(茨城県)は、七つの住棟により囲まれた二つの中庭をもち、屋根葺材には地元で焼かれた瓦を使用する等、周辺との融和に配慮された地上3階建ての低層集合住宅である。
茨城県営松代アパート(茨城県)は、中庭を囲む6階建ての4棟の住棟を、4階にある「上の道」と称する回廊でつないだ集合住宅であり、「上の道」は、プレイロットや植栽等のある街路状の空間として機能させることを意図している。
草加松原団地(埼玉県)は、高度成長期に建設された中層集合住宅を中心とする郊外型大規模住宅団地である。
同潤会江戸川アパート(東京都)は、関東大震災後の住宅難に対処するために設立された同潤会による、6階建のコの字型住棟と4階建の板状住棟が中庭を囲むRC造の中層集合住宅である。
東雲キャナルコート(東京都)は、工場跡地に建設された高層板状住棟の賃貸集合住宅である。6街区に分割されていて、1・2街区は中廊下式で住戸密度を高め、通風採光を確保するため中廊下に接続したテラスが特徴である。1街区の住戸には、仕事場等として使用できる開放的な「f-ルーム(ホワイエルーム)」を設け、中廊下やコモンテラスと連続させている。
世田谷区深沢環境共生住宅(東京都)は、木造平家建ての住宅団地の建替え事業により建築された公営の住宅であり、高木の保存、井戸の活用、優良土壌の再利用、古材の使用等、既存の環境の継承を意図し、高齢者在宅サービスセンターを併設した、シルバーハウジング・プロジェクトを含むものである。
かんかん森(東京都)は、各住戸の独立性を保ちつつ、居住者が共同で使用することができる居間や台所等を設置して、コモンミールや掃除等、生活の一部を共同化している、コレクティブハウスである。
SHARE yaraicho(東京都)は、道路に面する部分は巨大な半透明のテント膜で覆われ、内部は吹抜け空間を介して個室7室とコモンスペースが計画された、シェアハウスである。
求道學舎(東京都)は、武田五一設計による元学生寮を、コーポラティブハウスとして再生したものである。
用賀Aフラット(東京都)は、道路に対して視覚的に開放されつつ、ガラススクリーンで隔てられた中庭をもつ、アーティストやデザイナーの入居を想定した賃貸集合住宅である。
ひばりが丘団地(東京都)は、解体せずに再生・活用する技術的手法を検証するため、解体予定の住棟を用いてストック再生実証試験が行われた団地である。
晴海高層アパート(東京都)は、2戸×3層の6住戸を1単位とし、3層ごとに共用廊下を設け、そこから上下階の住戸に階段でアクセスするスキップアクセス形式を採用した都市型高層賃貸集合住宅である。
ライブタウン浜田山(東京都)は、1階のフラット住戸に設けられた専用庭と2〜3階のメゾネット住戸への専用の屋外階段が、路地的なスペースに面して設けられた集合住宅である。
タウンハウス諏訪(東京都)は、複数住棟の共用の庭をもち、また、各戸の専用庭及び住棟の雁行配置(各住戸を斜めにずらして配置したもの)により住戸の独立性を高めた集合住宅である。
りえんと多摩平(東京都)は、多世代の居住者が暮らす新たな街に生まれ変わらせる団地再生事業の一つとして、民間事業者が改修工事を行い、団地の一部の住棟をシェアハウスとして再生した。
プロムナード多摩中央(東京都)は、街区のほぼ中央にある歩行者専用道に面した接地階の住戸に、居住者が趣味や創造活動のアトリエ、教室等に利用することを想定した「フリースペース」と称する一室を設けることによって、沿道の賑わいや親しみのある景観形成を意図している。また、ストリート型住宅の実例でもある。 ストリート型住宅は、集合住宅の接地階部分において、居住者が日常生活の延長として、街並みの形成に参画できるような配慮を行うことによって、街路の活性化を意図した集合住宅の住戸形式をいう。
ベルコリーヌ南大沢(東京都)は、マスター・アーキテクト方式による一体感のある景観をもつ集合住宅地である。
インナートリッププラザ神山町(東京都)は、各階に多様な世帯構成を想定した各種の住戸を配置し、相互扶助的な共生を意図したコレクティブハウスである。
八潮ハイツ(東京都)は、日本勤労者住宅協会によって東京湾埋立地に建設された、リビングアクセス型の高層集合住宅である。
幕張ベイタウンパティオス 4 番街(千葉県)は、壁面線の位置・高さ、壁面率等についての「都市デザインガイドライン」に沿って設計された集合住宅であり、街区型の形式に特徴がある。
桜台コートビレッジ(神奈川県)は、西向きの急斜面に対して住戸の軸を45度に振り、雁行した平面によりバルコニーや開口部に変化を与え、プライバシーの確保を図った集合住宅である。
岐阜県営住宅ハイタウン北方-南ブロック(岐阜県)は、昭和40年代に建設された公営住宅の建替えに当たって、21世紀に向けた居住様式を提案することを目標として設計された集合住宅団地である。
ユーコート(京都府)には、住戸と住戸とのコミュニケーションを考慮した「つづきバルコニー」が設けられており、住棟に囲まれた敷地中央のまとまった共用緑地や広場からアクセスする多様な住戸を、居住者が設計に参加するコーポラティブ方式により建設した集合住宅である。
コモンシティ星田A2(大阪府)は、敷地内の緩斜面を活かした緑道の配置や、塀・門を極力設けない外構計画等により、連続した開放的な外部空間を創り出した戸建ての住宅団地である。
NEXT21(大阪府)は、二段階供給方式(スケルトン・インフィル分離方式)と環境共生をテーマにし、住戸の外壁等の規格化・部品化による可変性の確保や屋上植栽等が試みられた集合住宅である。
真野ふれあい住宅(兵庫県)は、阪神淡路大震災の被災者を対象に建築されたコレクティブハウスであり、共同の食堂、台所等を設けて居住者が生活の一部を共同で行うことが可能となっている。
グループハウス尼崎(兵庫県)は、阪神・淡路大震災後に被災した高齢者を対象に建設された、公営住宅である。
芦屋浜高層住宅(兵庫県)は、5層ごとに共用の憩いの場等である空中庭園をもつ、工業化工法による集合住宅である。
六甲の集合住宅Ⅰ、Ⅱ期(兵庫県)は、緑豊かな急斜面に沿った規則的な格子状の空間構成の中にテラスや中庭的空間を配して、自然や眺望を活かした住戸を創出している。
基町団地(広島県)は、戦災者応急住宅であった木造老朽住宅地区の再開発により建設された、高層高密度の集合住宅である。
ネクサスワールドのレム棟・コールハース棟(福岡県)は、各戸に採光と通風を確保するためのプライベートな中庭が設けられた接地型の集合住宅である。
補足:ネクサスワールドは、磯崎新がコーディネーターとなり、国内外の6名の建築家(スティーブン・ホール、レム・コールハース、石山修武 他)が設計した集合住宅団地。
熊本県営竜蛇平団地(熊本県)、中庭や共用部に面して住戸ごとの土間やテラス等を設け、居住者同士が互いの生活を感じながら居住することができるように計画されている。
熊本県営保田窪第一団地(熊本県)は、三つの住棟、集会室及び中央広場で構成され、中央広場については、住戸又は集会室を介してアクセスする居住者専用のものである。
再春館製薬女子寮(熊本県、妹島和世)は、80人が集まって生活することに重点を置き、居住者全員で使用するリビングスペースや浴場等の共用空間の充実を図った。
Mポート(熊本県)は、居住者の参加によって各住戸の設計が行われたコーポラティブハウスであり、居住者の交流等を意図して共用空間を配置した。
海外の集合住宅
シーランチ・コンドミニアム(アメリカ)は、10戸の週末用住居群を海の眺望を考慮して、敷地の勾配に沿って中庭を囲むように配置した低層集合住宅である。
レイクショアドライブ・アパートメント(アメリカ)は、ミース・ファン・デル・ローエにより設計された鉄骨造の高層集合住宅で、国際様式(インターナショナル・スタイル)の代表作である。
アビタ’67(カナダ)は、コンクリートボックスの組合せによって構成された高層集合住宅である。
ジェミニ・レジデンス(デンマーク)は、港湾施設として使用されていたサイロを改修し、集合住宅へ再生させたものである。
バイカー再開発(イギリス・ニューキャッスル)は、住民の意見を積極的に取り入れたもので、既存のコミュニティー施設を残し、地区の周囲に壁状の高層住棟を配置し、その内側に庭付きの低層集合住宅を配置した計画である。
ロメオとジュリエット(ドイツ)は、ハンス・シャロウンにより設計された高層集合住宅で、東西に伸びる敷地には、その西側に弧を描くように「ジュリエット」が、東側に塔状の「ロメオ」が対照的な形態で配置されている。
ヴァイセンホーフ・ジードルング(ドイツ)は、ミース・ファン・デル・ローエが全体計画を行った実験住宅展で建築された住宅団地であり、「インターナショナル・スタイル(国際様式)」の成立に影響を与えたものである。
マルセイユのユニテ・ダビタシオン(フランス、ル・コルビュジエ)は、ピロティのある高層集合住宅であり、メゾネット型住戸を主として建築物内には住戸に加えて、店舗、ホテル、屋上庭園等の機能がある。
ムードンの住宅(フランス)は、ジャン・プルーヴェによって設計された住宅群であり、アルミニウム等の材料が用いられている。
フランクリン街のアパート(フランス)は、オーギュスト・ペレによって設計された集合住宅であり、構造を鉄筋コンクリート造とした初期の集合住宅とされている。
ハーレン・ジードルンク(スイス)は、アトリエ5によって設計されたテラスハウス形式の低層集合住宅で、斜面地の地形を生かした階段状の構成が特徴である。
トーレ・ヴェラスカ(イタリア)は、BBPR(建築家グループ)によって設計された高層集合住宅で、下層部と上層部で意匠を切り替えた形態をもち、下層に店舗・上層に集合住宅をもつ。
カサ・ミラ(スペイン)は、アントニ・ガウディにより設計された高層集合住宅で、曲面を多用した波打つような石造ファサードと、鉄製バルコニー手摺の装飾が特徴のアール・ヌーヴォー建築である。
事務所建築
丸の内ビルディング(東京都、2002 年)は、旧丸の内ビルヂング(1923年)を建て替えた超高層ビルである。低層部には旧丸ビルの外観意匠を継承したデザインが採用されており、内部にはアトリウムが設けられている。
新宿NSビル(東京都)の高層階のオフィスゾーンは、中央にアトリウムを設け、事務室沿いの廊下をアトリウムに面して配置しており、その廊下から建築物のどこの位置に自分がいるのかを把握することができる。
三井本館(東京都)は、国の重要文化財に指定された建築物であり、重要文化財特別型特定街区制度を適用して超高層ビルと一体的に再生され、現在でも銀行やオフィスビルとして利用されている。
ROKI Global Innovation Center(静岡県)は、執務スペースが階段状に積層する立体的なワンルーム空間に、ガラスをはめこんだ木と鉄のハイブリッドトラスの屋根をかけ、自然光を通すフィルターを使用した天幕を設けている。
ジョンソン・ワックス・ビル(アメリカ)の 2 層吹抜けの執務スペースでは、天井付近が広がった樹木状の柱や柱頭まわりの天窓、ハイサイドライトによって、内部に自然を再現している。
フォード財団本部ビル(アメリカ)は、ビル内部に豊かな植栽が施されたアトリウムをもち、各フロアの執務スペースはアトリウムをL字型に囲むように配置されている。
クライスラービル(アメリカ)は、幾何学図形をモチーフにした記号的表現を特徴とするアール・デコ様式の高層オフィスビルである。
ロイズ・オブ・ロンドン(イギリス)は、機械設備、エレベーター、便所、階段等のサービス機能をもったシャフトを、建築物の外周部に独立して配置している。
香港上海銀行本店(香港)は、吊橋の工法を応用した構造の採用により、各階は、2列のマスト状の組柱の間が開放的な無柱空間となっている。
公共建築等
住田町役場(岩手県)は、凸レンズ状に組まれたトラス梁が並んだ屋根架構をもつ建築物である。
石巻市庁舎(宮城県)は、百貨店を転用したもので、既存エスカレーターをそのまま活用し、売り場は執務スペースへ、映画館は議場へと改修された。
国見町庁舎(福島県)は、主要構造部の柱や梁には、鋼材を内蔵した集成材を使用し、外壁にはガラスカーテンウォールと木製ルーバーを使用した建築物である。
大田区役所本庁舎(東京都)は、1990年代に建てられた民間企業のテナントビルを大田区が購入し、転用した区庁舎である。
目黒区総合庁舎(東京都)は、1960年代に民間企業の本社屋として建築された建築物を、耐震補強や設備改修等を行ったうえで、庁舎として転用したものである。
東京駅丸の内駅舎(東京都)は、赤レンガのファサードをもつ駅舎であり、 特例容積率適用地区制度を活用して、未利用容積を周辺建築物に売却・移転したうえで、保存・復原したものである。また、耐震改修において免震レトロフィット工法が採用された建築である。
すみだ生涯学習センター(東京都)は、公民館、文化ホール、情報センターの機能を独立して管理しやすいように別棟で計画し、それぞれをブリッジでつないでいる。
聖路加国際病院(東京都)は、特定街区制度を採用し、老朽化した病院を建て替えて、新たな都市環境の形成を図ったもので、520床のほぼ全病室が、シングルケアユニットと呼ばれるトイレ、シャワー付きの個室で構成されている。
山梨市庁舎東棟(山梨市)は、1970年代に建設された工場を、プレキャスト鉄筋コンクリート部材のアウトフレームを用いて耐震改修し、庁舎へ再生させたものである。
茅野市民館(長野県)は、公開プロポーザルコンペを経て選ばれた設計者と市民の代表とが、それぞれの場所や施設に関して数多くの論議を重ね、市民主導の計画により建設された。
旧大社駅舎(島根県)は、瓦屋根と漆喰壁による純日本風の木造平屋建ての駅舎である。
広島平和記念資料館(広島県)は、丹下健三によって設計され、1955年に開館した戦後モダニズム建築の代表作である。シンプルで装飾を排した外観、ピロティ構造、縦ルーバーが特徴である。
旧門司税関(福岡県)は、明治・大正時代の歴史的建造物を活かしたまちづくりである「門司港レトロ事業」の一環として、明治45年に建築された税関庁舎を、 港湾緑地の休憩所等として再生・活用したものである。
名護市庁舎(沖縄県)は、空調設備に依存することなく快適な環境をつくりだすために、屋上を緑化したり、風の道を確保するなどの計画がなされている。また、各階をセットバックさせてできたテラスをパーゴラで覆う等して、屋根・外壁・開口部を日射と風雨から保護し、日陰となるスペースをつくりだしている。
ジョン F. ケネディ国際空港 TWAターミナルビル(アメリカ):長さ約105mの屋根は、4本のY字柱脚に支えられた4枚の鉄筋コンクリート造によるシェルで構成されている。
パイミオのサナトリウム(フィンランド)は、アルヴァ・アアルトによって設計された結核患者が療養するための病院で、合理的で明快なゾーニングと風土に根ざしたヒューマン・デザインが特徴である。
西洋建築史
(概ね建築年代順)
パルテノン神殿(ギリシャ)は、エンタシスのある柱をもつドリス式の神殿建築であり、ギリシャ建築の代表例である。
パンテオン (ローマ)は、れんが及びコンクリートにより造られた大ドームを特徴とした、ローマ建築の代表的な建築物である。直径約43mのドームは、上方へいくほどドームの厚さが薄くなっている。
コロッセウム(ローマ)は、4層の立体構成をもち、1層目をドリス式、2層目をイオニア式、3層目をコリント式とし、各層で異なるオーダーを装飾的に用いたローマ建築の代表例である。
ハギア・ソフィア大聖堂(トルコ)は、バシリカ形式とドーム集中形式とを融合させた平面をもち、巨大なドーム構造によって内部に広大な空間を作り出したビザンチン様式の建築物である。直径約31mの中央の大ドームは、その東西にある2つの半ドームと南北にある4つの巨大なバットレスで支えられている。
アーヘンの宮廷礼拝堂(ドイツ)は、平面が八角形の身廊とそれを囲む十六角形の周歩廊があり、身廊の上部にはドーム状のヴォールトをもつ集中式の建築物である。(様々な建築様式が混在しています)
コルドバの大モスク(スペイン)は、紅白縞文様の2段アーチを伴って林立する柱による内部空間をもち、現在はキリスト教文化とイスラム教文化が混在している建築物であり、イスラム建築の代表例である。
サン・マルコ大聖堂(イタリア)は、ギリシア十字形の集中式プランをもち、中央の交差部及び十字架の4枝の上にドームをもつイタリアのビザンチン建築である。
シュパイヤー大聖堂(ドイツ)は、内陣の前に袖廊(トランセプト)を配したラテン十字形の三廊式バシリカの平面に、西面の中央と両端、身廊・側廊と袖廊との交差部、内陣の両側に塔をもつ、ロマネスク様式の建築物である。
ピサ大聖堂(イタリア)は、ラテン十字形のプランをもち、会堂部は五廊式、袖廊部は三廊式、交差部に楕円形のドームをもつイタリアのロマネスク建築である
ダラム大聖堂(イギリス)は、天井面に交差リヴ・ヴォールトが採用された最古のロマネスク様式の大聖堂である。
ヴォルムス大聖堂(ドイツ)は、東西両端にアプスを対置させた二重内陣と身廊の両側に側廊を設けたバシリカ形式で構成され、東西の内陣と交差部とに六つの塔をもつロマネスク様式の建築物である。
ル・トロネ修道院(フランス) は、ロマネスク様式の建築物であるが、装飾を排除した、粗い石積みだけの限られた要素で構成されている。
パリのノートルダム大聖堂(フランス)は、二重周歩廊をめぐらした内陣と階上廊を有する側廊が設けられた五廊式バシリカの平面に、バラ窓や双塔を西面にもつ、ゴシック様式の建築物である。
アミアン大聖堂(フランス)は、身廊部・袖廊部ともに三廊式であり、内陣に周歩廊と放射状祭室とをもつフランスの盛期ゴシック建築である。
ケルン大聖堂(ドイツ)は、ゴシック様式のキリスト教会堂であり、双塔をもつ西正面とリブ・ヴォールト天井を備えた身廊を特徴とする。
アルハンブラ宮殿(スペイン)は、イスラム式の宮殿建築で、複数の中庭、アーケード、塔等がある。
ミラノ大聖堂(イタリア)は、多数の小尖塔の外観を特徴とした、ゴシック建築の代表的な建築物である。
サンタ・マリア・デル・フィオーレ [フィレンツェ大聖堂](イタリア) は、世界最大級の石積ドームをもち、外装はピンクや緑の大理石により幾何学模様で装飾され、クーポラとランターンは初期ルネサンス様式、ファサードはネオ・ゴシック様式の建築物である。
ローマのテンピエット(イタリア) は、16世紀のルネサンス建築である。小規模な集中式の円形礼拝堂で、古代ローマの円形神殿をモチーフとしている。
バシリカ・パラディアーナ(イタリア)は、2層のアーケードを持つファサードが特徴のルネサンス建築の代表例である。
サン・ピエトロ大聖堂(ヴァチカン)は、ルネサンスからバロックの時代にかけて建築されたカトリックの教会であり、ルネサンス建築とバロック建築両方の様式が内在する。
サン・カルロ・アッレ・クァットロ・フォンターネ聖堂(イタリア)は、楕円形のドームと、凹凸の湾曲面や曲線が使用されたファサードをもつバロック建築である。
ヴェルサイユ宮殿(フランス)は、広大かつ整然とした幾何学的庭園をもち、宮殿内は 「鏡の間」に代表される豪華な室内装飾が随所に施された、バロック様式の建築物である。
ロンドンのセント・ポール大聖堂(イギリス) は、18世紀のバロック建築である。ロンドン大火によって被災した大聖堂を立て替えてできた、イギリス最大のモニュメントとされる。
ウェストミンスター宮殿(イギリス)は、国会議事堂として使われており、北端のエリザベス・タワー(ビッグベンの愛称で呼ばれる時計塔)、南西のヴィクトリア・タワー、および中央塔を備える、ネオ・ゴシック様式の建築物である。
サグラダ・ファミリア(スペイン)は、アントニ・ガウディにより設計されたカトリック教会堂である。曲線や有機的形態を多用した独自の構造により、ゴシック様式やアール・ヌーヴォー様式を融合させた造形が特徴であり、立面には精緻な彫刻装飾が施されている。
寺社仏閣・城等
中尊寺金色堂(岩手県)は、外観が総漆塗りの金箔押しで仕上げられた方三間の仏堂であり、平安時代に建てられた建築物である。
日光東照宮社殿(栃木県)は、本殿と拝殿との間を石の間でつないだ権現造りの例である。
円覚寺舎利殿(神奈川県)は、禅宗様(唐様)の建築であり、禅宗様(唐様)において、組物は、柱頭だけでなく柱間にも並び、組物間の空きが小さいことから詰組み(つめぐみ)と呼ばれている。また、上部が曲線をなす開口部は火灯(かとう)と呼ばれ、鎌倉時代後半に初めて用いられている。また、主体部の柱と裳階の柱を海老虹梁でつないでいる。
臨春閣(大正期に移築、現・神奈川県)は、3棟からなり、現在の第三屋においては、1階に雅楽の楽器を用いた欄間、2階に縁を配した小部屋が設けられている、江戸時代に建てられた数寄屋風書院造りの建築物である。
如庵(愛知県)は、17世紀にもと建仁寺内に造立された、大小五つの窓や躙口の配置が特徴的な茶室である。今は犬山城東にある日本庭園有楽苑にある。国宝に指定されています。
園城寺光浄院客殿(滋賀県)の平面は、「匠明」の殿屋集に描かれている「主殿の図」とほぼ同じであり、桃山時代の標準的な武家の住宅の形式を示すものと考えられている。
伊勢神宮内宮正殿(三重県)は、平入りで、切妻屋根に竪魚木(かつおぎ)と千木(ちぎ)をもち、柱を全て掘立て柱とした神明造りの例である。また、東西に隣接する南北に細長い二つの敷地のうち、式年遷宮によって交替で一方の敷地を用いて、造替が繰り返されてきている。
賀茂別雷神社本殿・権殿(京都府)は、切妻造り、平入りの形式をもち、前面の屋根を延長して向拝を設けた、流造りの例である。
賀茂御祖神社(京都府)は、切妻造り、平入りで屋根の前面を葺き下ろしにして向拝を設けた、流造りである。
慈照寺東求堂同仁斎(京都府)は、銀閣と同じ敷地に建ち、現存する最も古い違い棚と付書院をもつ「四畳半」である。慈照寺東求堂の同仁斎は、四畳半茶室の起源といわれる。
東福寺竜吟庵(京都府)は、東福寺の塔頭であり、現存する最古の方丈といわれている。
塔頭とは、大寺院の敷地内にある小寺院などをいう。方丈は住職の居所のこと。
二条城二の丸殿舎(京都府)の黒書院には、押板床・違棚・付書院をもつ上段の間がある。
桂離宮(京都府):江戸時代における公家の社会においては、王朝文化を反映した別荘等が造営され、桂離宮は数寄屋風建築の代表例である。
笑意軒(京都府)は、17世紀に桂離宮の敷地南端に造立された、茅葺寄棟屋根や深い土庇等の農家風の外観をもつ格式にこだわらない自由な造形の茶室である。
平等院鳳凰堂(京都府)は、中堂の左右に重層の翼廊が配置されており、平安時代に建てられた建築物である。
本願寺飛雲閣(京都府)は、敷地内の池に面して建つ3層の楼閣建築であり、左右対称を避けるように3層を中央からずらして配置し、屋根や唐破風を複雑に配した建築物である。外観、内部ともに住宅風に造られており、軽快で奇抜な意匠が施されている。
妙喜庵待庵(京都府)は、16世紀に造立された、千利休が建てた二畳の草庵茶室である。また、待庵は国宝に指定されており、現存する最古の草案茶室とも言われている。
密庵(京都府)は、大徳寺の書院内にある茶室四畳半台目で、書院と草庵が融合した書院風の茶座敷であり、小堀遠州によって造立されたといわれている。国宝に指定されています。
孤篷庵忘筌(京都府)は、17世紀に小堀遠州によって造立された、縁先にわたした中敷居の上の障子とその下の開口が特徴的な書院風茶室である。
鹿苑寺金閣(京都府、室町時代)は、方形造りの舎利殿で、最上層を禅宗様仏堂風、二層を和様仏堂風、初層を住宅風とした三層の建築物である。
清水寺本堂(京都府)は、長い束柱(つかばしら)を貫で固めた足代(あししろ)によって、急な崖の上に張り出した床を支える懸造(かけづくり)の建築物である。
法隆寺東院伝法堂(奈良県)は、桁行が7間であるが移建前は5間であり、聖武天皇橘夫人の邸宅の一屋を移して建立したものと考えられている。
法隆寺金堂(奈良県)は、重層の入母屋造りの屋根をもち、飛鳥様式で建てられた堂であり、構造上の特徴として、天秤式に釣り合うように計画された雲形組物を有する建築物である。
薬師寺東塔(奈良県)は、三手先の組物を用い、裳階(もこし)が付いた三重塔である。各層に裳階を付け、六つの屋根が交互に出入りする独特の構造を有する建築物である。
裳階は、身舎の軒下に付く庇状の構造物のことで、薬師寺東塔を例にすると下から1,3,5番目の小さな屋根を指す。
新薬師寺本堂(奈良県)は、一重の入母屋造りで、桁行5間、梁間3間の身舎(もや)の周囲に1間の庇を設けている。
唐招提寺金堂(奈良県)は、一重、寄棟造りであり、前面1間を吹放しとしている。
春日大社本殿(奈良県)は、春日造りであり、春日造りは、切妻造り、妻入り、丹塗りとし、正面柱間は1間のものが多く、土台を設けている。
東大寺南大門(奈良県)は、貫で軸部を水平方向に固め、挿肘木を重ねて軒の荷重を支える大仏様の建築物である。
今西家住宅(奈良県):江戸時代における商家は、町家の一つであり、今西家のように、表通りに面し、片側が土間で奥に座敷を設けたものがある。
住吉大社本殿(大阪府)は、住吉造りであり、住吉造りは、切妻造り、妻入りとし、平面は前後に外陣・内陣に分かれ、 前後に細長い形状であり、回り縁・高欄はない形式である。
姫路城(兵庫県)は、平地の小丘を巧みに利用して構築された平山城であり、大天守と小天守の外観の優美さが特徴である。白漆喰で塗られた美しい外観が、羽を広げて飛び立つ白鷺の姿に似ているため「白鷺城」とも呼ばれる。
浄土寺浄土堂(兵庫県)は、太い虹梁(こうりょう)と束を積み重ねて屋根を支える構造の大仏様(天竺様)の建築物である。
箱木家住宅(兵庫県)は、屋根を棟束で支え、柱間が長く、内法高の低い、現存最古級の一つと推定されている民家である。
三徳山三仏寺投入堂(鳥取県)は、修験の道場として山中に営まれた三仏寺の奥院であり、岩山の崖の窪みに建てられた懸造り(かけづくり)である。
出雲大社本殿(島根県)は、切妻屋根の妻側に入口のある妻入り形式の大社造りの例で、入口が一方に偏った左右非対称の形式を持つ。
厳島神社社殿(広島県)は、神体山とする宮島の弥山を祀るために島の海浜に設けられており、本殿は身舎の前後に庇を付けた両流造りの例である。
宇佐神宮本殿(大分県)は、八幡造りである。八幡造りは、切妻造り、平入りとし、前殿と後殿とを連結し、両殿の間に生じた屋根の谷に陸樋を設けている。
東三条殿(京都府、平安時代)などの寝殿造りは、柱は丸柱とし、寝殿の周囲には蔀戸(しとみど)を吊り、床は板敷きであったといわれている。寝殿造りにおいて、寝殿の左右や後ろに造られた独立の住屋は、対屋(たいのや)と呼ばれ、渡殿(わたどの)で連結されている。
その他
陸前高田のみんなの家(岩手県)は、東日本大震災の津波で立ち枯れたスギの丸太を用い、被災した人々の集いの場としてつくられた集会場である。
中京郵便局(京都府)は、明治時代に建てられた煉瓦造の洋風建築であり、ファサードの一部を保存し、内部を一新して鉄筋コンクリート造の建築物とすることにより、現在でも郵便局として利用されている。
ウィーン郵便貯金局(オーストリア、オットー・ヴァグナー):過去の様式からの離脱(分離)を図り、新しい造形表現を主張するゼツェッシオン「分離派」を背景としている。
アインシュタイン塔 (ドイツ、エーリッヒ・メンデルゾーン) は、アインシュタインの相対性理論を実測検証するために建てられた、太陽観測所で、コンクリートを用いた有機的なフォルムを特徴とした、ドイツ表現主義の代表例である。
ロンシャン教会堂(フランス、ル・コルビュジエ)は、コンクリートのもつ重量感を巧みに引き出し、彫刻作品を思わせる独創的な建築物である。
ジオデシック・ドームは、バックミンスター・フラーにより考案されたドームの形式の総称であり、モントリオール万国博覧会のアメリカ館では、鋼材の立体トラスとガラスによって巨大な球体のドームを実現させた。
解体等の理由によりマップに未登録の建築事例一覧
中野本町の家(伊東豊雄)
から傘の家(篠原一男)
私たちの家(林昌二・林雅子)
増沢邸[自邸](増沢洵)
斎藤助教授の家(清家清)
正面のない家-H(坂倉準三建築研究所)
原自邸(原 広司)
塔の家(東 孝光)
立体最小限住居(東京都、池辺陽)
夫婦屋根の家(神奈川県、山下和正)
軽井沢の山荘(吉村順三)
住吉の長屋(安藤忠雄)
フィッシャー邸(ルイス・カーン)
夏の家(スウェーデン、E. G. アスプルンド)
釜石・平田地区仮設住宅団地(岩手県)
同潤会江戸川アパート(東京都)
晴海高層アパート(東京都)
東三条殿(平安時代)
ジオデシック・ドーム:ドームの構築法であり、ジオデシック・ドームの例は幾つもあります。
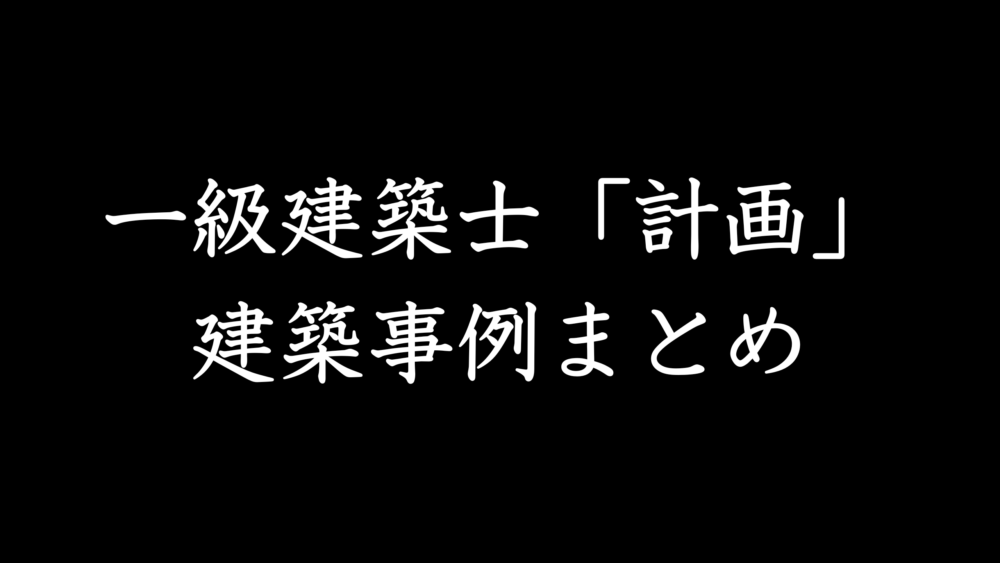

コメント